過去に起きた信じられない名勝負をまとめて紹介します!
今回はTOP10のうち10位から6位まで紹介
【前半】10位 → 6位(徹底解説)
選定方針
- 舞台性:街の景観・ナイトレースの臨場感がドラマを増幅したか
- レース内容:オーバーテイク、戦略、ペナルティ、赤旗・SCの扱いなど“物語の濃さ”
- 歴史的影響:チャンピオンシップやチーム体制に与えた波及
- 映像の記憶:あとから見返しても語り継がれる象徴性
※「市街地」の定義上、モナコ/シンガポール/アゼルバイジャン(バクー)/ラスベガス/マイアミ/ジェッダ(サウジ)などを中心に選出しています。
第10位:2019年 シンガポールGP
ベッテル、誇りを取り戻した“逆転のアンダーカット”
ナイトレースの金字塔・シンガポールで、フェラーリの戦略が鮮烈に決まった一戦。通常、このコースはオーバーテイクが難しく、ピット戦略=順位の命綱。当時チーム内の主導権を急速に握りつつあったルクレールに対し、ベッテルは“先に止めて後から抜く”アンダーカットで逆転。ピットアウト時に渋滞をすり抜ける“クリアトラック”を得て、一気にトップを奪い返しました。
どこが名勝負?
- 戦略の妙:アンダーカットを最大化する“ピットアウト先の交通整理”が鍵。エンジニアリングと運が噛み合った。
- 心理戦:若手エース台頭の最中、ベッテルが示した“老練”。モノサシがスピードだけでないことを証明。
- 歴史性:ベッテルにとって大きな意味を持つ勝利。フェラーリのナイトレース強さの記憶にも直結。
今見るなら
1回目のピットイン直前のラップタイム推移、ピットアウト時の“クリア”具合、そして無線のテンポ感。画面の外で進む“将棋”を、光と影のコントラストが劇的に映し出します。
第9位:2023年 ラスベガスGP
ペナルティ、接触、そしてラストラップの大逆転劇
砂漠の夜、ネオンのストリップを走る“ショーとレースの融合”。初年度から波乱続きで、スタート直後の接触や5秒ペナルティなどイベントごとに議題が噴出。それでもレースは失速せず、終盤に三強の駆け引きが凝縮。中でもハイライトは最終盤、ブレーキング勝負が生む“逆張りのライン取り”でした。トップ争いの二者が先の周回から準備していた温存とタイヤ温度の作法が、最後の数コーナーで爆発。**ラスベガスは単なるショーではなく“勝負のリング”**であることを証明しました。
どこが名勝負?
- レギュレーションと臨機応変:制裁を受けても“取り返す”冷静さ。現行F1に必要な“可変戦術”の見本。
- ブレーキングの美学:低μのナイトストリートで、限界ギリギリまで突っ込む勇気とコントロール。
- 都市×F1の新解釈:映像体験の圧が、レースの“記憶密度”を高めることを証明。
今見るなら
DRSゾーン前の“スリップを与えないライン”、そして最終ラップの駆け引き。**“抜き返しの布石”**の置き方が上手い。
第8位:2017年 シンガポールGP
史上稀有の“雨スタート市街地”。タイトルの風向きを変えた一撃
市街地×雨=視界ゼロ。しかもシンガポールでのウェット・スタートは初の事例に近い難条件。フロントロウのフェラーリ勢とレッドブルが1コーナーまでの半周足らずで絡み、多重クラッシュ。タイトル争いの行方が、暗闇のスコールで一変しました。中段から冷静にレースを拾い上げたメルセデスが、**“荒天の生存力”**を見せつける形に。
どこが名勝負?
- スタート100mの縮図:視界・グリップ・位置取りが1秒で並び替わる。市街地の“逃げ場のなさ”が影響を増幅。
- リスク管理の勝利:“勝ちに行く”より“落とさない”判断がタイトルの加点に直結。
- F1の非情:最速のクルマが勝つとは限らない。天と地と運の方程式が、ストリートではしばしば逆転する。
今見るなら
オンボードで見る水煙の壁と、イン側アウト側の選択。スタートの1秒前のステアの向きまで面白い。
第7位:2021年 サウジアラビアGP(ジェッダ)
赤旗、再スタート、疑惑のブレーキング——スローモーションで進む心理戦
超高速ストリート・ジェッダは、**“モンツァ級の速度×壁の近さ”**が特徴。赤旗とSCがレースを刻み、再スタート=やり直しが勝負を混ぜ返す。タイトルを争う二人のアグレッションは、譲る・譲らない・譲るフリの心理戦にまで発展し、接触とペナルティが重くのしかかる。それでも最後の最後まで“勝ち筋”の探索を止めない、人間の強度が剥き出しになった一戦でした。
どこが名勝負?
- ルールの縁で戦う:再スタートの並び順、譲り方、ラインワーク……規則と駆け引きの境界線。
- オンボードの迫力:300km/h超で壁スレスレ。ミス=即、代償。
- “勝ちたい”感情の可視化:無線・ボディランゲージ・スロー再生……全部が物語になる密度。
今見るなら
赤旗ごとに変わるタイヤ選択、再グリッドの位置交渉、そして“譲ると見せての踏み直し”。1コーナーのアプローチ角がすべてを語る。
第6位:2017年 アゼルバイジャンGP(バクー)
大混乱のフラッグ・フェスト。Ricciardoの“下克上”とStrollの衝撃表彰台
SC連発、接触、パーツ破損、手順違反の疑惑——カオスの全メニューが山盛り。“旧市街の狭路+超ロングストレート”というバクーの二面性が、混乱=チャンスを最大化した典型例です。序盤は下位に沈んでいたリカルドが、ダブルオーバーテイク級の決定打で上位へ急伸。さらにはヘッドレストの不具合でピットを余儀なくされた王者候補、SC中の“当てた/当てない”論争、そしてストロールの初表彰台。最後の直線でボッタスが写真判定級の差で2位をもぎ取るエンディングまで、1周たりとも退屈なし。
どこが名勝負?
- “運”を味方にする技:荒れたレースほど再始動の温度管理/ブレーキの作法/瞬時の判断が差になる。
- バクーという装置:狭いのに長い。“詰まり”と“伸び”の両極がカオスを増幅。
- ヒーロー誕生:下位発進の快勝、若者の大舞台デビュー——“語り”が多い。
今見るなら
再スタート直後のターン1飛び込みと、DRS解禁直後のスリップ合戦。SC明けに**誰がどれだけ“暖められていたか”**が丸見えです。
まとめ(前半)
市街地レースの魅力は、コースの“逃げ道のなさ”がドラマを凝縮する点にあります。
- 戦略が順位をひっくり返す(2019シンガポール)。
- ショーの街が本気の勝負のリングに変わる(2023ラスベガス)。
- 天候ひとつで物語が書き換わる(2017シンガポール)。
- 規則と心理の綱引きが炙り出される(2021ジェッダ)。
- 混乱が英雄を選ぶ(2017バクー)。
この“前半”では10位から6位までを深掘りしました。“後半”は5位から1位へ。伝説級の名勝負(モナコの歴史的バトル、シンガポールの“事件”、バクーの劇的フィナーレなど)を、同じ密度で掘り下げます。
市街地は壁が近く、路面もサーキットと違い滑るので、少しの操作ミスでクラッシュしてしまいますよね。
だからこそ、F1ドライバーのすごさがよくわかります。
過去映像を見るためには高速のネットワークが大事!↓↓




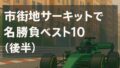
コメント